


日常生活や仕事・学校などのストレスに適応できず、不安、抑うつ、イライラ、意欲低下などの症状が現れる病気です。環境の変化や人間関係が引き金となることが多く、ストレスの原因から離れると症状が改善することもあります。
しかし、放置するとうつ病などへ進行する可能性があるため、早めの対応が重要です。

気分の落ち込みや意欲低下が長期間続き、日常生活に支障をきたす病気です。
興味や喜びの喪失、不眠、食欲不振、集中力の低下などの症状が現れ、重症化すると自殺のリスクも高まります。
過度なストレスや環境要因が発症のきっかけとなることが多く、適切な治療と周囲のサポートが重要です。
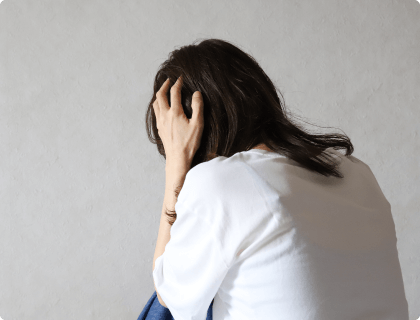
突然の強い不安や恐怖を伴うパニック発作が繰り返し起こる病気です。
動悸、息苦しさ、めまい、発汗、震えなどの身体症状を伴い、「このまま死んでしまうのではないか」という強い恐怖感が生じます。
発作への不安から外出を避けるようになり、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
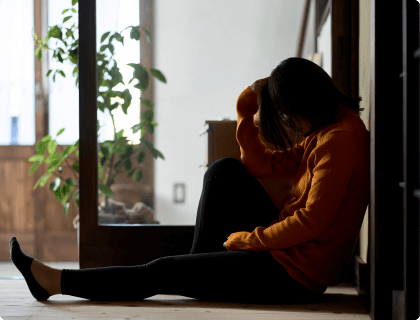
気分の波が大きく、躁状態(気分の高揚・過活動)と抑うつ状態(気分の落ち込み・意欲低下)を繰り返す病気です。
躁状態では睡眠が少なくても活動的になり、衝動的な行動をとることがあり、抑うつ状態では何もできなくなることがあります。
長期的な経過をたどるため、継続的な治療が必要です。

寝つきが悪い、中途で目が覚める、朝早く起きてしまうなどの睡眠の問題が続く病気です。
日中の疲労感や集中力低下を引き起こし、生活の質が著しく低下します。
ストレスや生活習慣が原因となることが多く、不眠が続くと精神的な不調を招くこともあるため、適切な対処が求められます。

注意力の持続が難しく、不注意・多動・衝動的な行動が特徴の発達障害です。
子どもの頃に診断されることが多いですが、大人になっても症状が続くことがあります。
学業や仕事、対人関係に影響を及ぼしやすく、環境調整や適切な支援が必要です。
自己管理が難しいため、時間管理やタスクの工夫が求められます。

対人関係の苦手さ、強いこだわり、コミュニケーションの難しさが特徴の発達障害です。
感覚過敏や特定の物事への強い興味を示すこともあります。
幼少期から症状が現れることが多く、日常生活や社会生活に影響を与えることがありますが、適切な支援や環境調整により生活の質を向上させることができます。
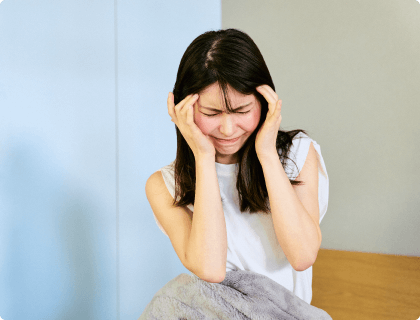
幻覚や妄想、思考の混乱などが特徴の精神疾患です。
実際には存在しない声が聞こえたり、自分が監視されていると感じたりすることがあります。症状が進行すると社会生活が困難になることがあり、早期の治療が重要です。
原因は完全には解明されていませんが、脳の機能異常が関与していると考えられています。

医学的な原因が見つからないにもかかわらず、痛みやしびれ、吐き気、疲労感などの身体症状が続く病気です。
ストレスや心理的要因が関与していることが多く、症状が長期化すると生活に支障をきたすことがあります。
適切な心理的サポートやストレス管理が重要であり、過度な検査や治療は避けることが推奨されます。

記憶力や判断力が低下し、日常生活に支障をきたす病気です。
初期は物忘れが目立ちますが、進行すると時間や場所が分からなくなったり、身の回りのことができなくなったりします。
アルツハイマー型や血管性認知症などの種類があり、進行を遅らせるための治療やリハビリが重要です。